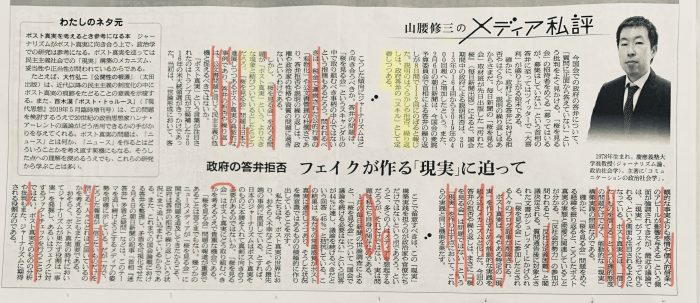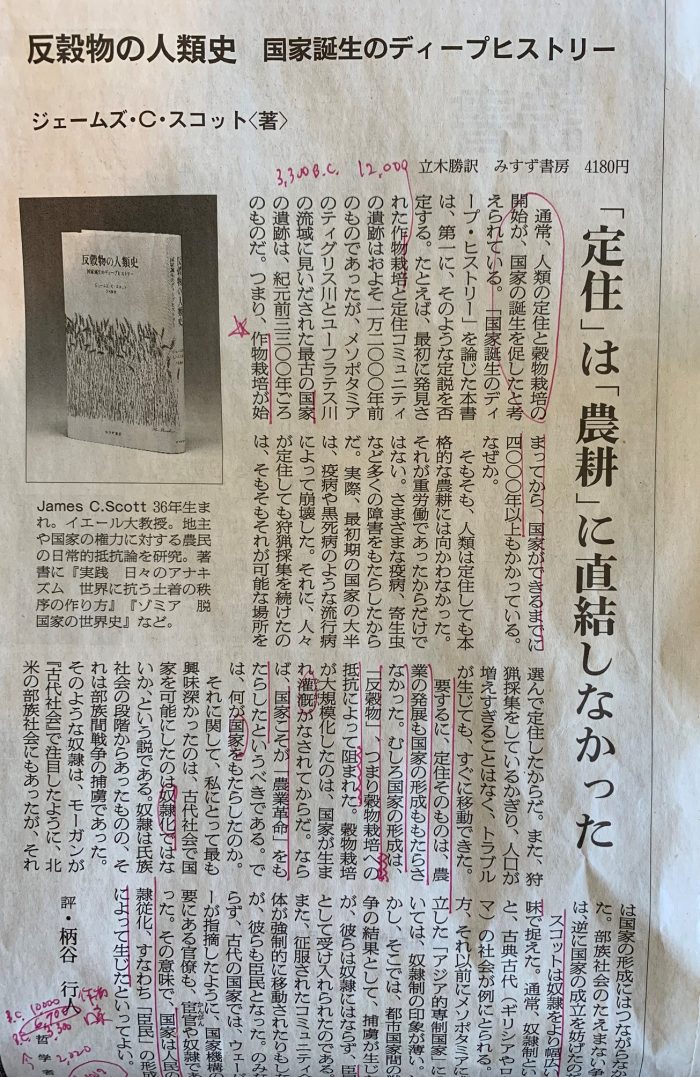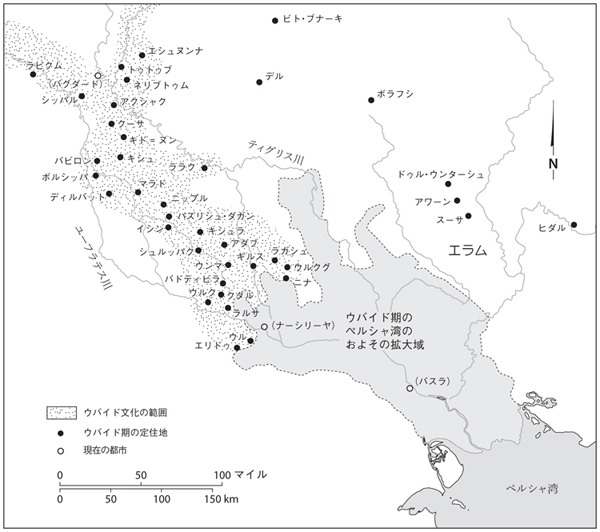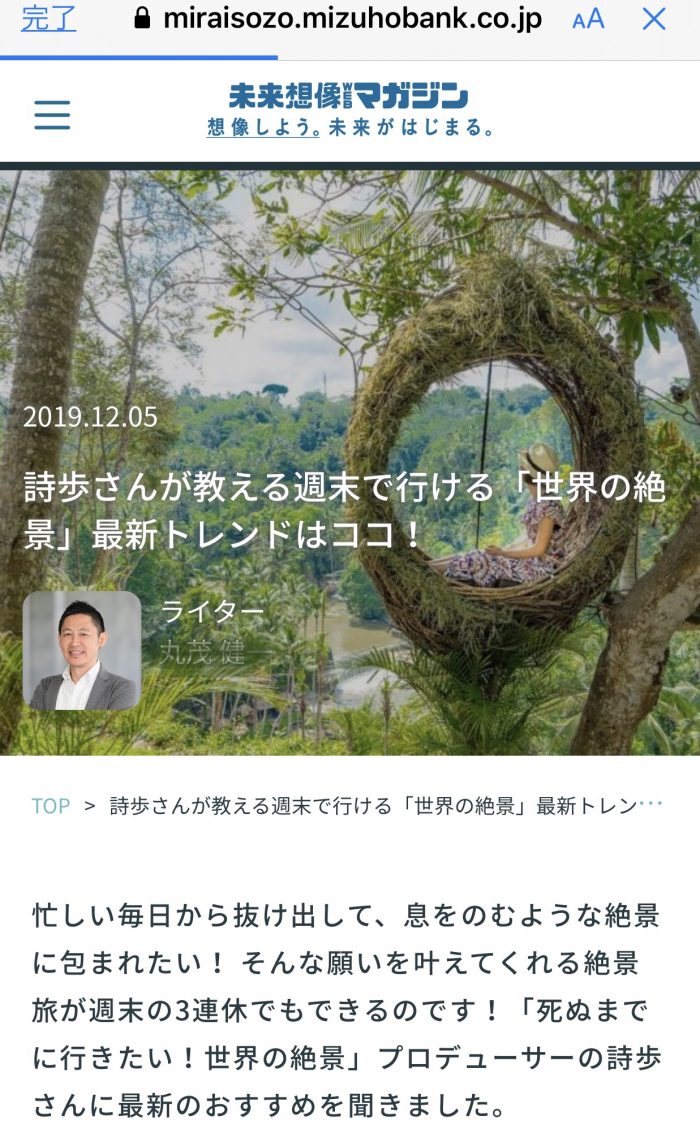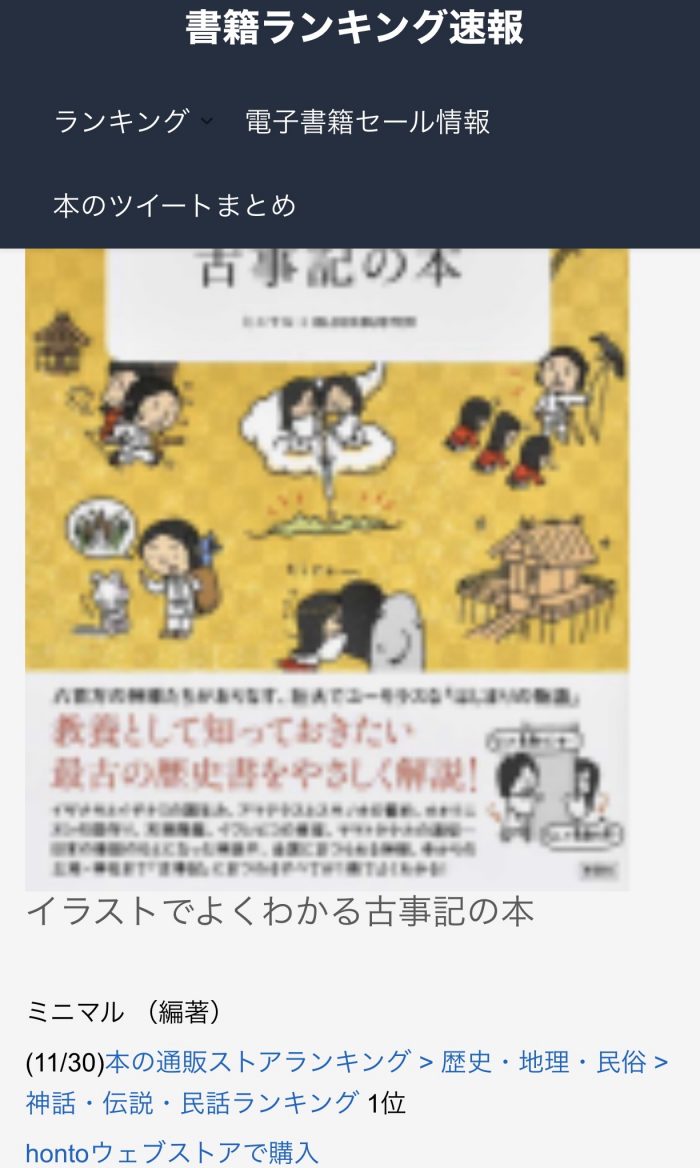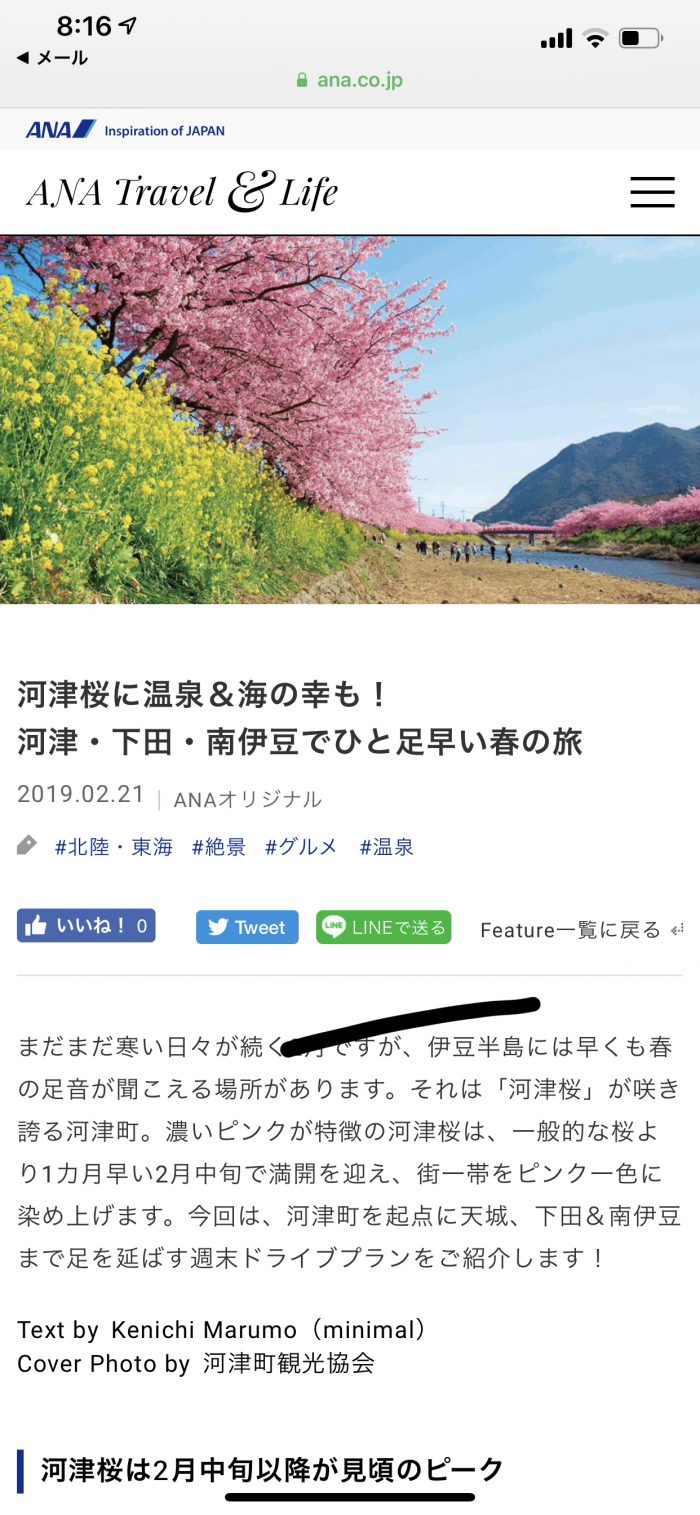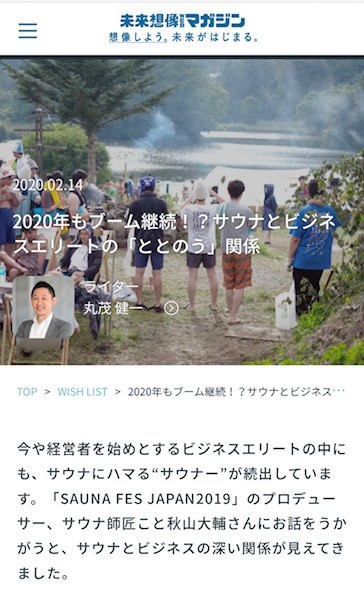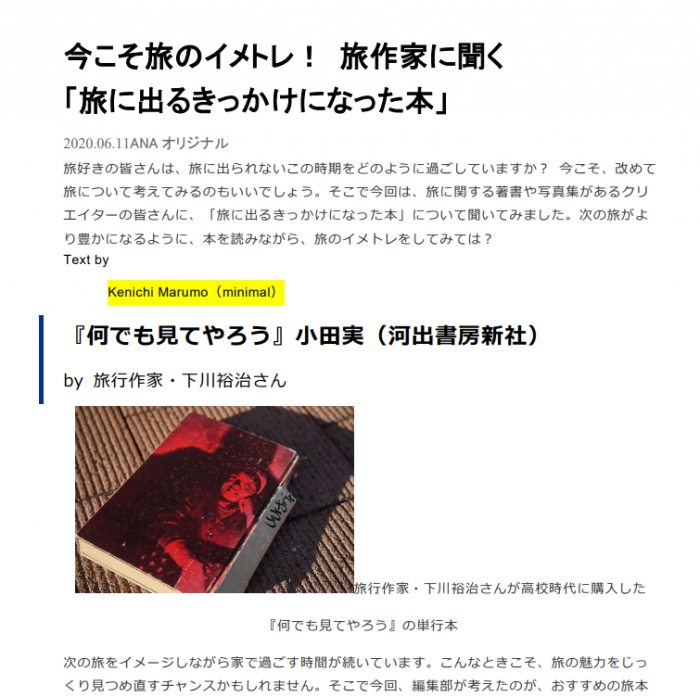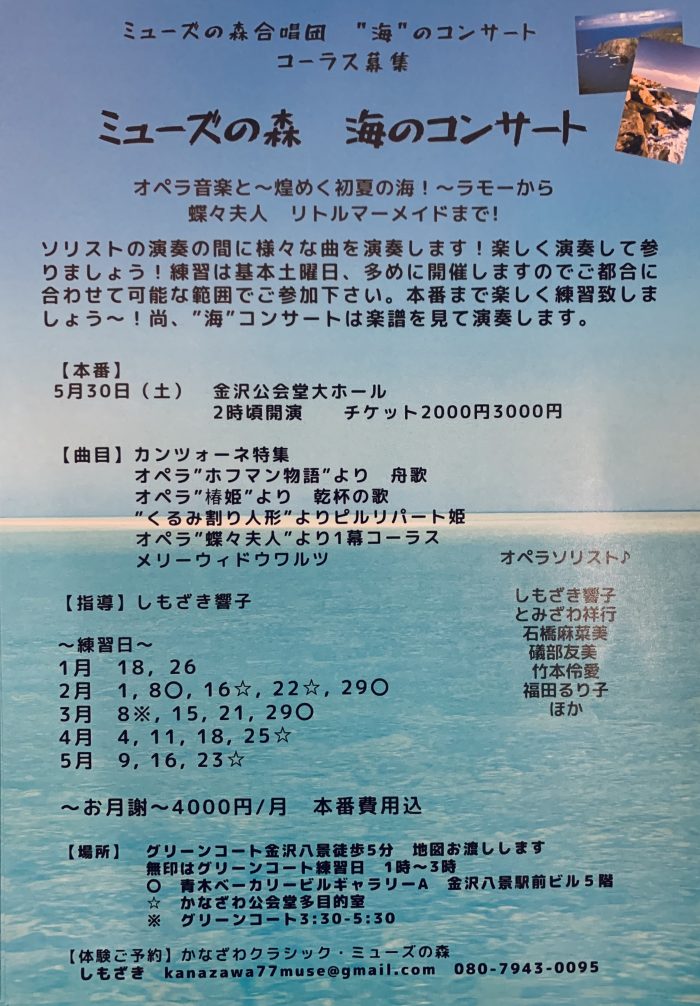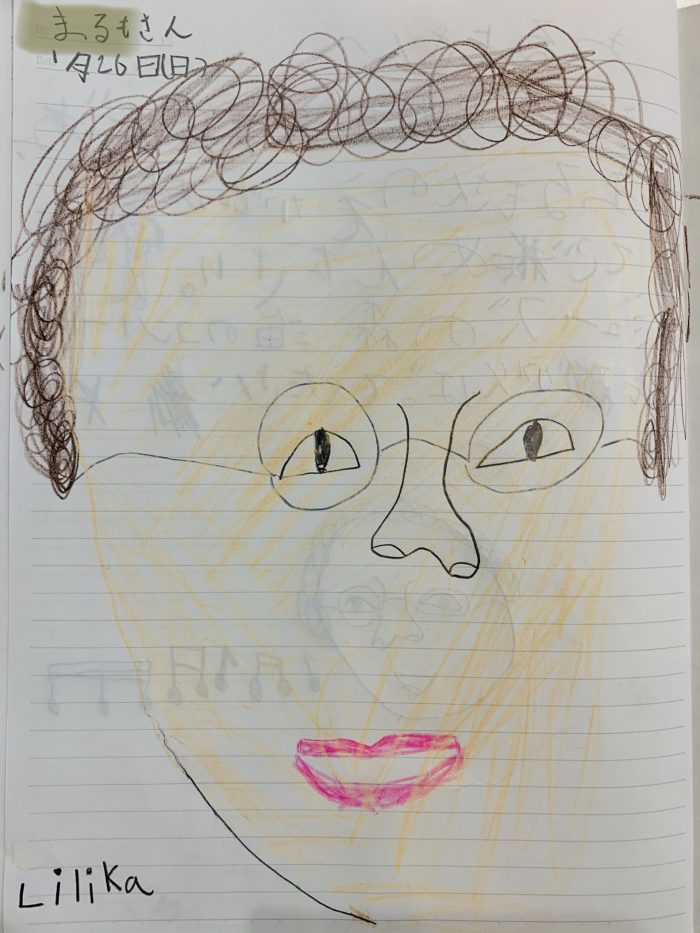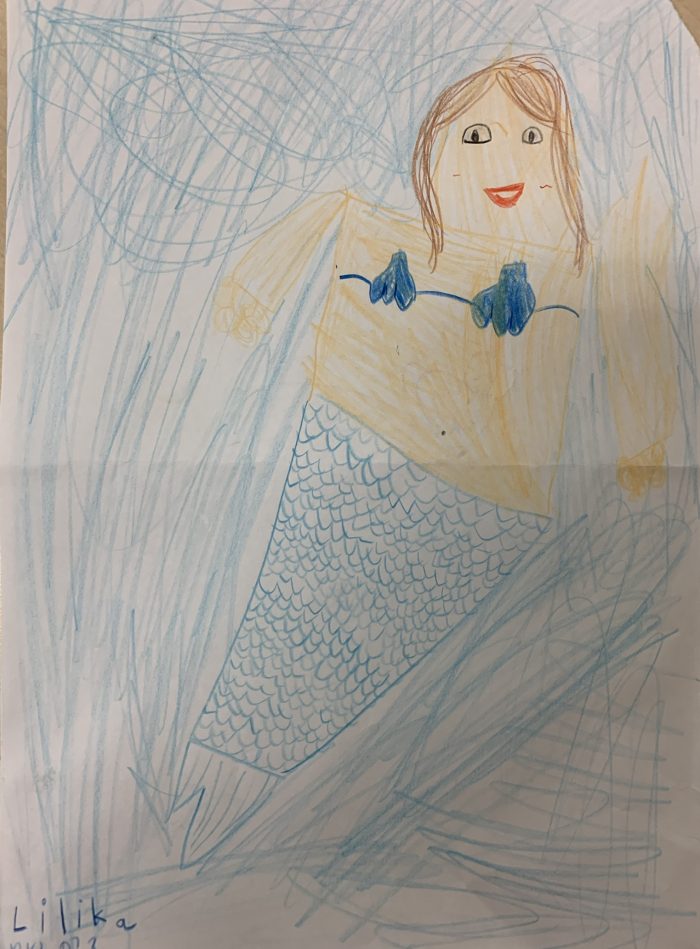♪ Malia: Tosti
Malìa(魅惑)はフランチェスコ・パオロ・トスティ(Francesco Paolo Tosti, 1846年~1916年)によって1887年に作曲されました。詩はロッコ・E・パッリアーラ(Rocco E. Pagliara, 1855年~1914年)によるものです。トスティはイタリアの作曲家で、主に歌曲を多く作曲しました。イタリア語はもちろん、英語、フランス語の詩も取り上げ、歌曲の芸術的評価を高めました。トスティの歌曲の美しい旋律と繊細な和音はたくさんの人に愛されているのではないでしょうか。
Luciano Pavarotti – Malia (Japan 2004)
| Cosa c’era ne ‘l fior che m’hai dato? forse un filtro, Un arcano poter! Nel toccarlo, il mio core ha tremato, m’ha l’olezzo turbato ‘l pensier! | あなたが私にくれた花の中には何が 入っていたの? きっと秘薬か神秘的な力だろう! それに触ると、私の心は震えた、 その芳香は私の気持ちを混乱させた! |
| Ne le vaghe movenze, che ci hai? un incanto vien forse con te? Freme l’aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa ‘l tuo piè! | 優美な物腰の中に、何があるのか? 魅惑がきっとあなたと共に 来るのだろうか? あなたの行くところの空気は震え、 あなたの足の通るところで花は咲く! |
| Io non chiedo qual plaga beata fino adesso soggiorno ti fu: non ti chiedo se Ninfa, se Fata, se una bionda parvenza sei tu! | 私は尋ねない どんなに幸せな地域に あなたがこれまで住んでいたのか、 私はあなたに尋ねない ニンフなのか、 妖精なのか、 あなたが金髪の見せかけなのか! |
| Ma che c’è nel tuo sguardo fatale? cosa ci hai nel tuo magico dir? se mi guardi, un’ebbrezza m’assale, se mi parli, mi sento morir! | しかし 何があなたの宿命的な 眼差しの中にあるのか?どんなものを あなたの魔法の言葉の中に持 っているのか? あなたが私を見ると、私は夢見 心地に襲われ、あなたが私に話 しかけると、私は死ぬ思いだ! |
| fiore/花 dare/与える forse/きっと filtro/秘薬 arcano/神秘的な potere/力 toccare/触る core/心 tremare/震える olezzo/芳香、香気 turbare/邪魔をする、混乱させる pensiero/考え、気持ち vago/優美な movenza/そぶり、物腰 avere/持っている incanto/魅惑 venire/来る con/~と共に fremere/震える aria/空気 dove/~であるところの vai→andare/行く spuntare/出る、姿を現す ove/~であるところへ passare/通る piè/足 | chiedere/求める、尋ねる plaga/広がり、地域 beato/最高に幸せな、幸せな fino/~まで adesso/今 soggiorno/滞在 se/~かどうか Ninfa/ニンフ、妖精 Fata/妖精、運命の女神パルカ biondo/金髪の parvenza/見せかけ、おもかげ sguardo/眼差し fatale/宿命的な magico/魔法の dire/言葉 guardare/見る ebbrezza/陶酔、夢見心地 assalire/攻める、襲う parlare/話す sentire/感じる、思う morire/死ぬ |