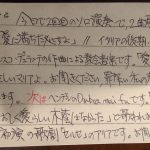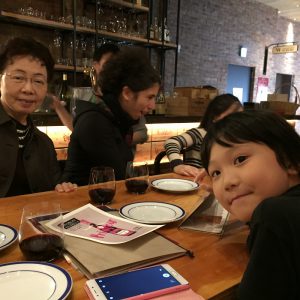♪O mio babbino caro♪
「opera?例えばどんな曲でしょうか?」と訊いたらこの曲が・・・。可能性はあるのだろうか。
from the one act Italian opera Gianni Schicchi by Giacomo Puccini
Libretto: Giovacchino Forzano |
 |
Italian LyricsO mio babbino caro,
|
English TranslationOh my dear father,
|
Maria Callas O Mio Babbino Caro Giacomo Puccini
ANNA NETREBKO
Accompaniment (Gmajor-low)




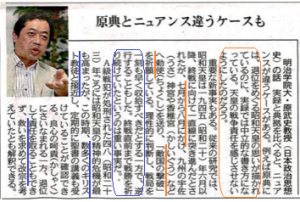






 沖縄からの視点
沖縄からの視点


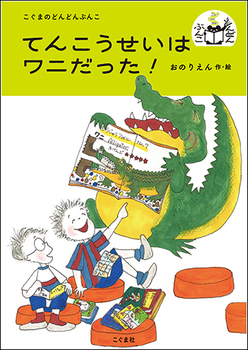
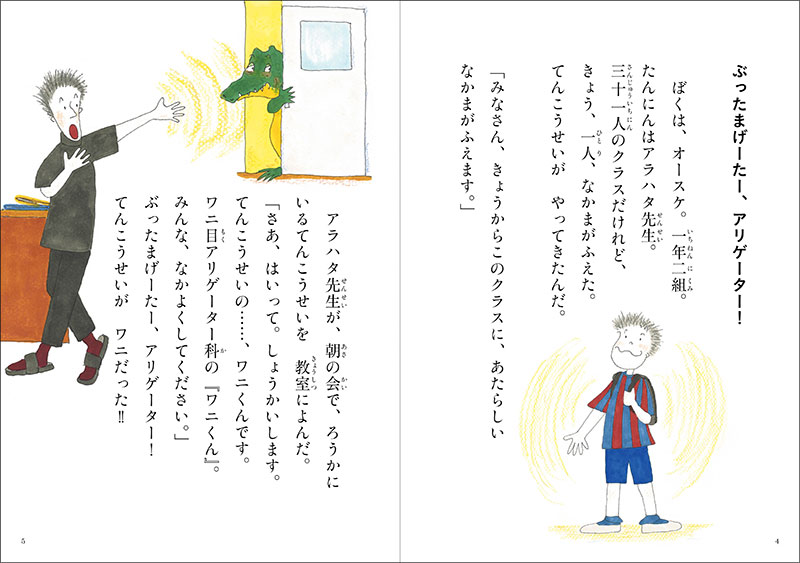
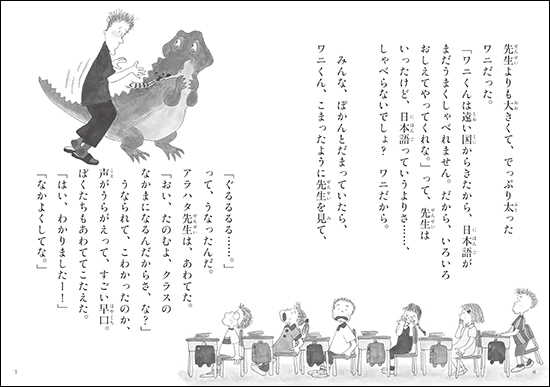
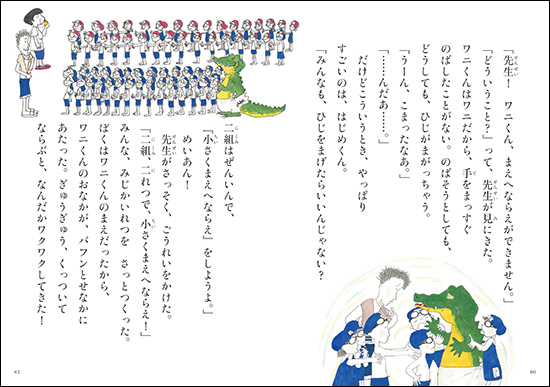







 イギリス館(British House Yokohama)
イギリス館(British House Yokohama)





 (紙片を見ながら曲の紹介)
(紙片を見ながら曲の紹介)