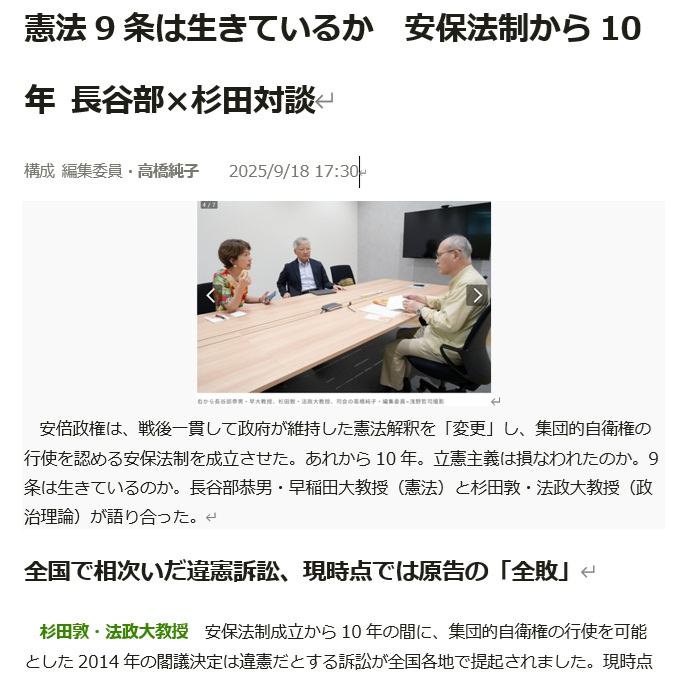5/3は憲法記念日。長谷部恭男先生は論旨がすっきり・わかりやすく、日本国憲法の良さをいつも教えてくれる人だ。政治・国際情勢・社会の諸問題は気になるけど「私が気にしなくてもいいか、、、?」と思ってしまう。でも時々はここにしっかり記録して折に触れ勉強するための「投稿」。勉強は楽しい。
<追加>(憲法9条は生きているか安保法制から10年)。2025/9/15
学術会議会員任命拒否問題をめぐって、これが「学問の自由」に関係があるのかないのかについて学者の中でも意見が分かれている。しかも「ある」という人も「ない」という人も自信をもって断言している。なぜこのようなことになっているのか。ここでは論争の構図を整理し、社会の中での学問の立ち位置について考えてみたい。
二種類の「学問の自由」
現在の論争で用いられている「学問の自由」という語は大きく二つの意味を担わされているように見える。一つは「自分の好きなように研究をする自由」(「学問の自由A」)。もう一つは「学問が権力による干渉を受けないこと」(「学問の自由B」)という意味である。今回の問題は「学問の自由」とは関係ない、なぜなら学術会議の会員にならなくても研究は自由にできるからだ、という人たちはこの言葉をAの意味でとらえている。それに対して、いや、問題は学問の自由に大いに関係があるという人たちは、特定の政権の意向に沿うだけなら学術会議は御用学者集団になってしまうとBの視点から危惧している。(以下略)
「公共の福祉(特に、表現の自由や学問の自由との調整)」に関する基礎的資料(PDF) 平成 16/4 / 1衆議院憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 TEXT

デジタル大辞泉 「学問の自由」の意味・読み・例文・類語
学問研究・研究成果の発表・討論・教授・学習などに関して、政治・宗教・経済などいっさいの外的権力からの干渉・制限・圧迫を受けることなく、活動しうること。 日本国憲法第23条に「学問の自由は、これを保障する」と規定されている。Jun 23, 2017
AI Overview
Learn more
学問の自由には、学問活動における他者からの干渉や制限を受けない自由という意味と、学問研究の自由、研究発表の自由、教育の自由といった具体的な内容が含まれます。これは、思想・良心の自由、言論・表現の自由とも関連し、真理の探究を保障する重要な権利です。
学問の自由の具体的な意味:
学問研究の自由:
どんな分野の学問を研究するのか、どのような方法で研究を行うのか、自己決定の自由。
研究発表の自由:
研究成果を自由に発表し、議論を深める自由。
教育の自由:
どのような教育内容を伝えるのか、どのような教育方法で教えるのか、自己決定の自由。
学問的活動の保護:
学問研究、研究発表、学説内容など、学問的活動とその成果が、国家権力やその他の外圧によって妨げられないこと。
大学の自治:
大学が国家権力等の外的干渉を受けずに、自主的に学問研究・教育に関する諸事項を決定・遂行する権利。
学問の自由の重要性:
社会の発展と進歩:学問の自由は、社会の発展、技術開発、生活の改善に貢献する。
民主主義社会の基盤:批判精神を育み、民主主義社会を支える。
真理の探究:学問研究を通じて、真理を探究し、知識を蓄積する。
個人の成長:学問の自由は、個人の知的好奇心と創造性を高め、個性的な能力を伸ばす。
学問の自由と関連する憲法上の条項:
憲法第23条:学問の自由を保障。
憲法第19条:思想・良心の自由を保障。
憲法第21条:言論、出版、集会、結社、表現の自由を保障。
学問の自由における大学の自治とは?判例も紹介します!
May 9, 2021 — 学問の自由とは、学問活動において他者から干渉や制限を受けない自由です。 日本においては、学問=心理…
生成 AI は試験運用中です。法的なアドバイスについては、専門家にご相談ください

5/7「トランプ支持勢力つなぐ「終末論」とは テック右派も宗教右派にも」
The governing ideology of the far right has become a 📛monstrous, supremacist survivalism. Our task is 📍to build a movement strong enough to stop them
The movement for corporate city states cannot believe it’s good luck.
For years, it has been pushing the extreme notion that wealthy, tax-averse people should up and start their own high-tech fiefdoms, whether new countries on artificial islands in international waters (“seasteading”) or pro-business “freedom cities” such as Próspera, a glorified gated community combined with a wild west med spa on a Honduran island. Full TEXT
それにしても、なぜこの政権はこれほどまでに「極端」なのか。その「原動力」はどこから来るのか。
謎を解くヒントとなる論考が、先月、🔹英国のガーディアン紙に載った。著者は著名な作家ナオミ・クライン氏とドキュメンタリー映画監督のアストラ・テイラー氏だ。「🌹終末論ファシズムの台頭」という題の長い論考だが、全体として、❗️トランプ政権を支える諸勢力は危険な「終末論」的思想で結びついているとして、警鐘を鳴らす内容となっている。(神里先生)

★「ゼロサム」思考のトランプ
https://www.akemimarumo.com/wp-content/uploads/2025/05/d2a7e52b205fdd27a0b9c1827e401a5e.pdfトランプ米大統領の世界観は「ゼロサム」思考に基づいている。すなわち「米国が勝つためには誰かが負けなければならない」とする考えで、両者が利益を得る「ウィンウィン」の発想はない。ゼロサムの対立構造はトランプ氏の人生を構成する不変の要素だ。トランプ氏は世界における米国の役割を縮小させたいと考えているのではないか。ロシアのプーチン大統領が支配したウクライナの広範な地域の運命は気にならないようだし、台湾についても関心は高くなさそうだ。このパラドックスは、トランプ氏が世界を勢力圏の概念で捉えていると考えると理解できる。full text

「トランプ氏の復権は「革命」 副大統領ブレーンが予測する帝国の時代」2025/5/9Asahi
Full Text 同志社大三牧さんのコメントが良い。
帝国の幻影~壊れゆく世界秩序~「勢力圏」のはざまで【6】 米国は第2次トランプ政権の下、自ら第2次世界大戦後に築き上げた「リベラルな国際秩序(Liberal International Order)」を壊すような動きを見せてきました。背景に何があり、今後の世界はどうなるのか。バンス米副大統領のブレーンである米ノートルダム大学のパトリック・デニーン教授
三牧聖子氏:「もちろん、トランプ政権に多くの人脈を有するデニーン氏の国際秩序観は、トランプ政権の行動を理解するには役立つ。就任以来トランプは、19世紀から20世紀にかけてアメリカの領土拡張のイデオロギーとなった「明白なる運命(manifest destiny)」という標語を掲げ、グリーンランドやパナマ運河への帝国主義的な欲求を露わにしてきた。ただ、これらの行動が、「腐敗したリベラルの平和的な転覆」とどうつながるのかは不明だ。少なくとも日本をはじめとする中小国から見れば、国際秩序を悪化させるだけの行動だ。」

🌷2025/9/15追加 (憲法9条は生きているか安保法制から10年)。。。
<追加の追加>「欧米がお手本だった意味2025/8/5」ポピュリズムの台頭、揺らぎの根に