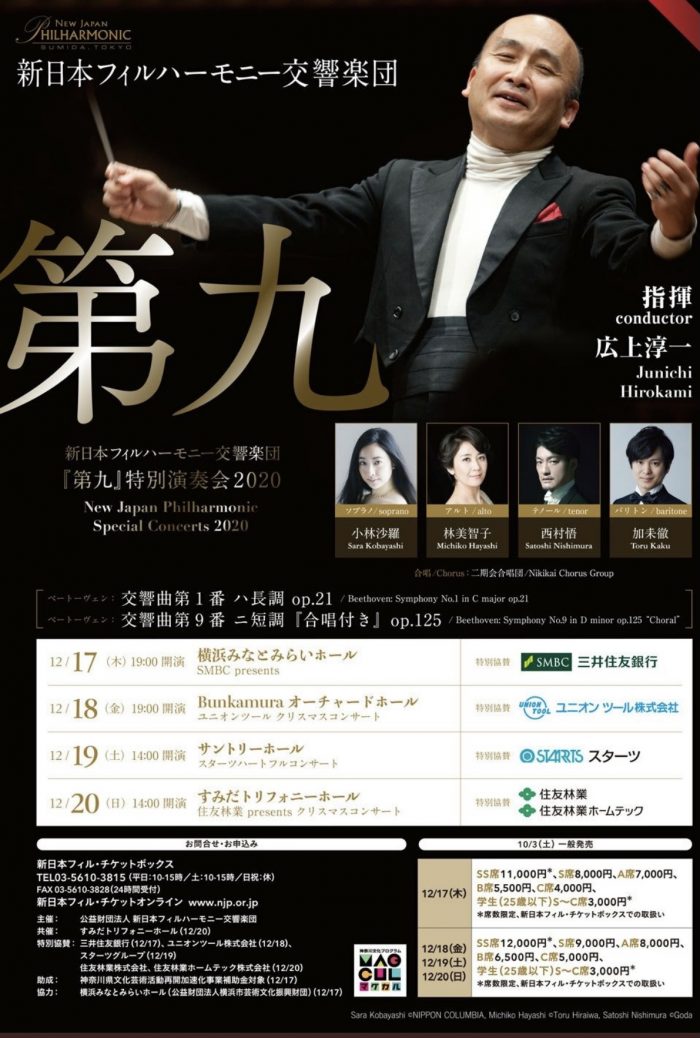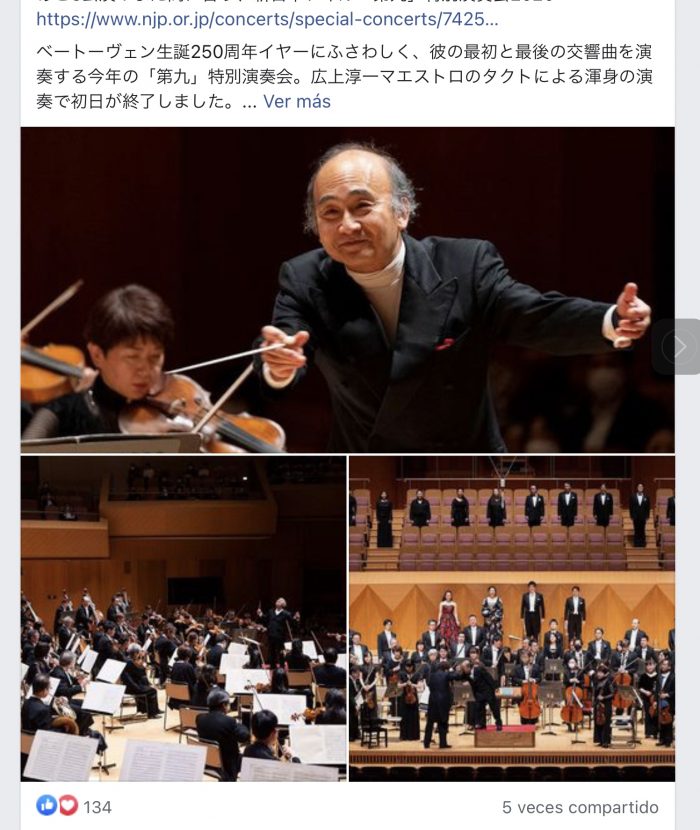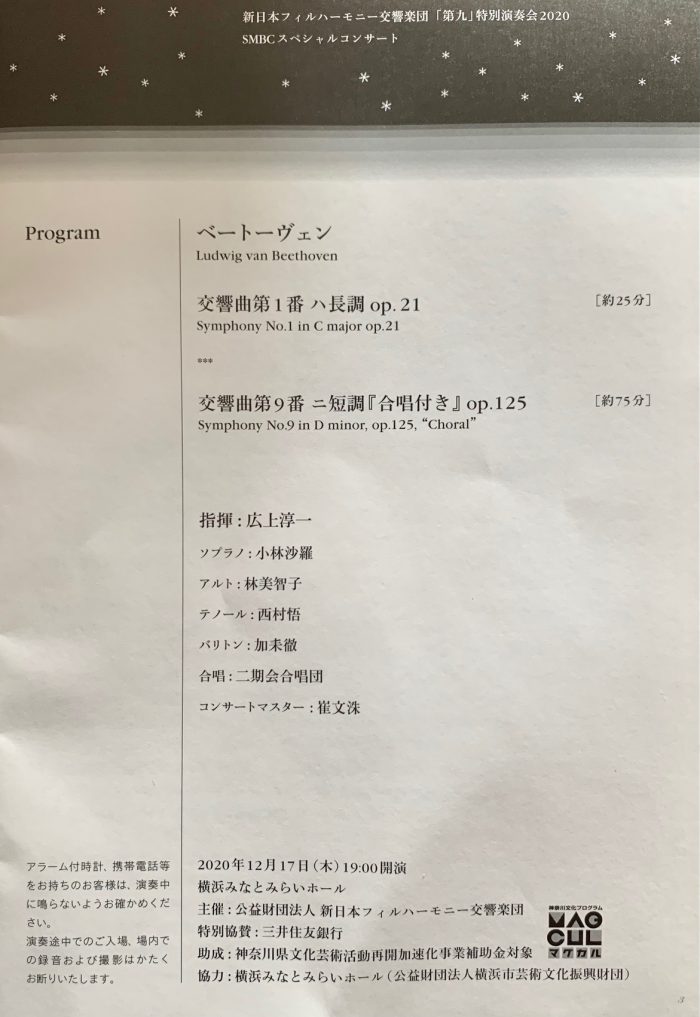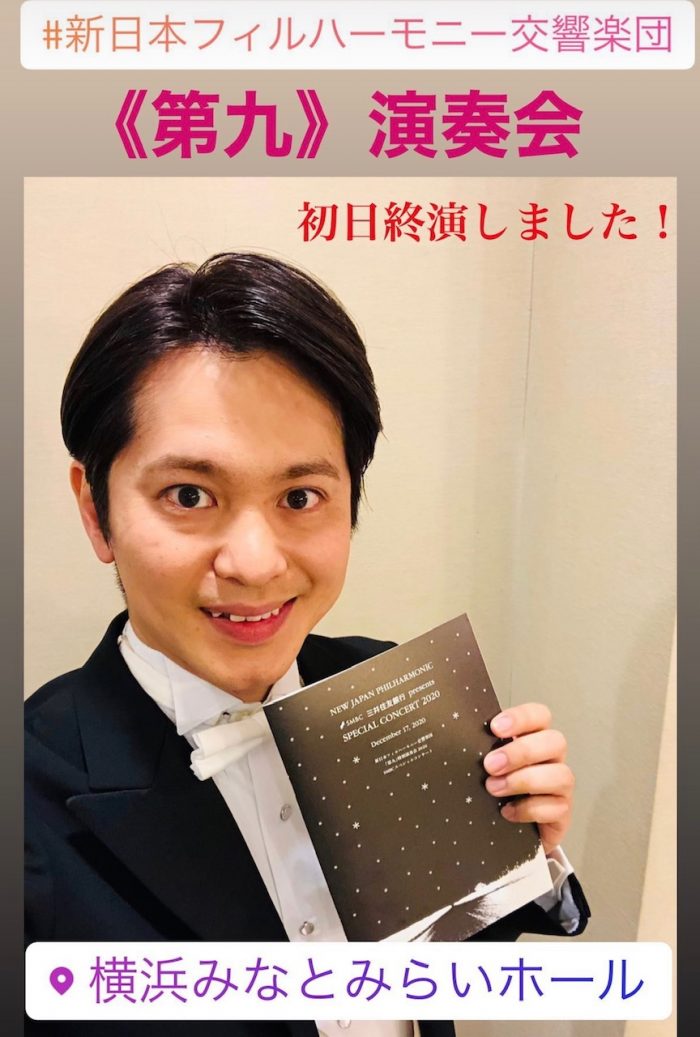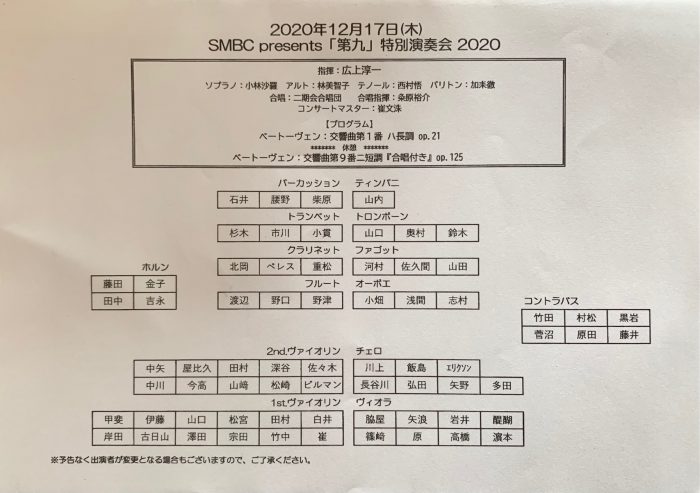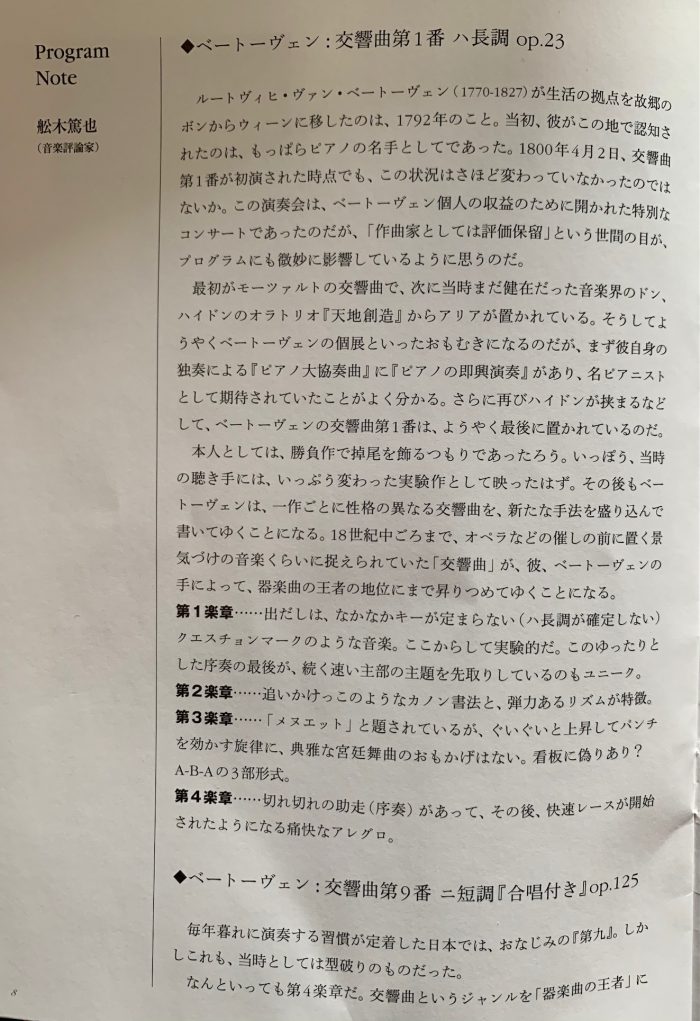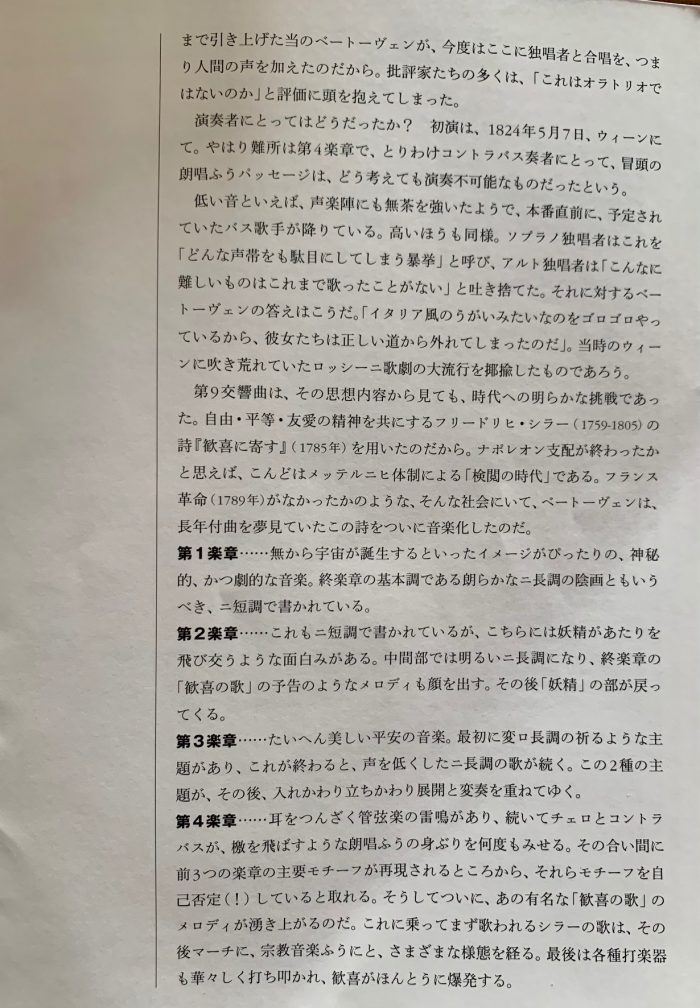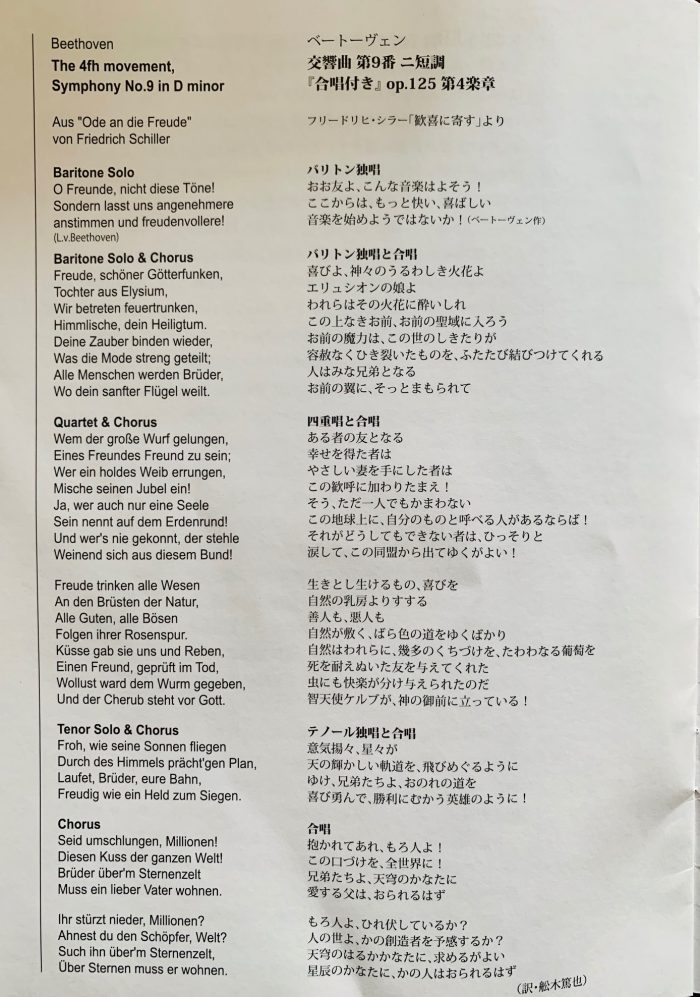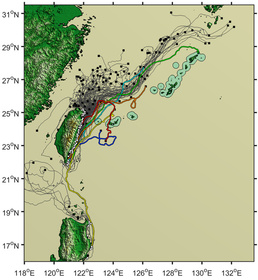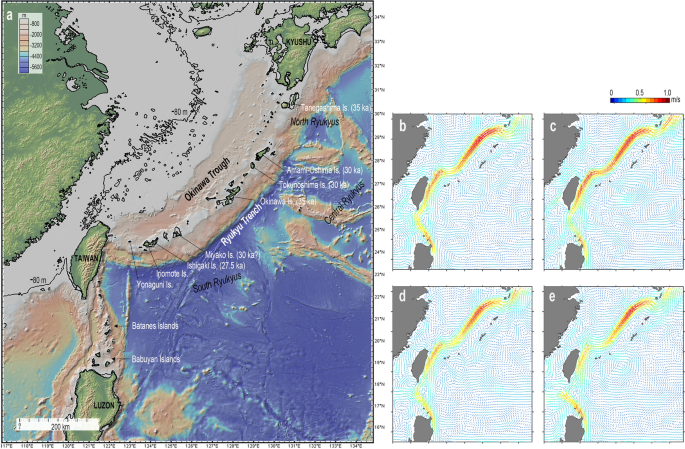初詣`どこかで春`も見つけたり
駅前の歯科からの帰り道になんだか人だかりが・・。瀬戸神社に長蛇の列(Social Distancingのため)。「おッと、初詣なのだ」と思いついて急遽参詣(Shintoistを自称している割には不真面目)。500円玉を用意してならんでいたら、すぐ前のお兄さんたちが千円札を用意しているのでちょっと気になったけど、そのまま。階段そばの狛犬がマスクをしていた!
正月の平潟湾
小さな草にも春がくる

アメリカフウロ 
イヌホウズキ 
ウスベニチチコグサ 
エゾムラサキ 
オウシュウヨモギ 
オオアレチノギク 
オニタビラコ 
オランダミミナグサ 
カタバミ 
(キイチゴ属) 
コハコベ 
スミレ/ハタザオキキョウ 
セイタカハハコグサ 
セイヨウオオバコ 
ゼニゴケ 
チチコグサモドキ 
ノゲシ 
ヒメスミレ 
ヒメツルソバ 
ヒメムカシヨモギ 
ホトケノザ 
ミミナグサ 
ヤブカンゾウ 
やわげふうろ
野草のART
八景ハイム敷地のタチツボスミレ