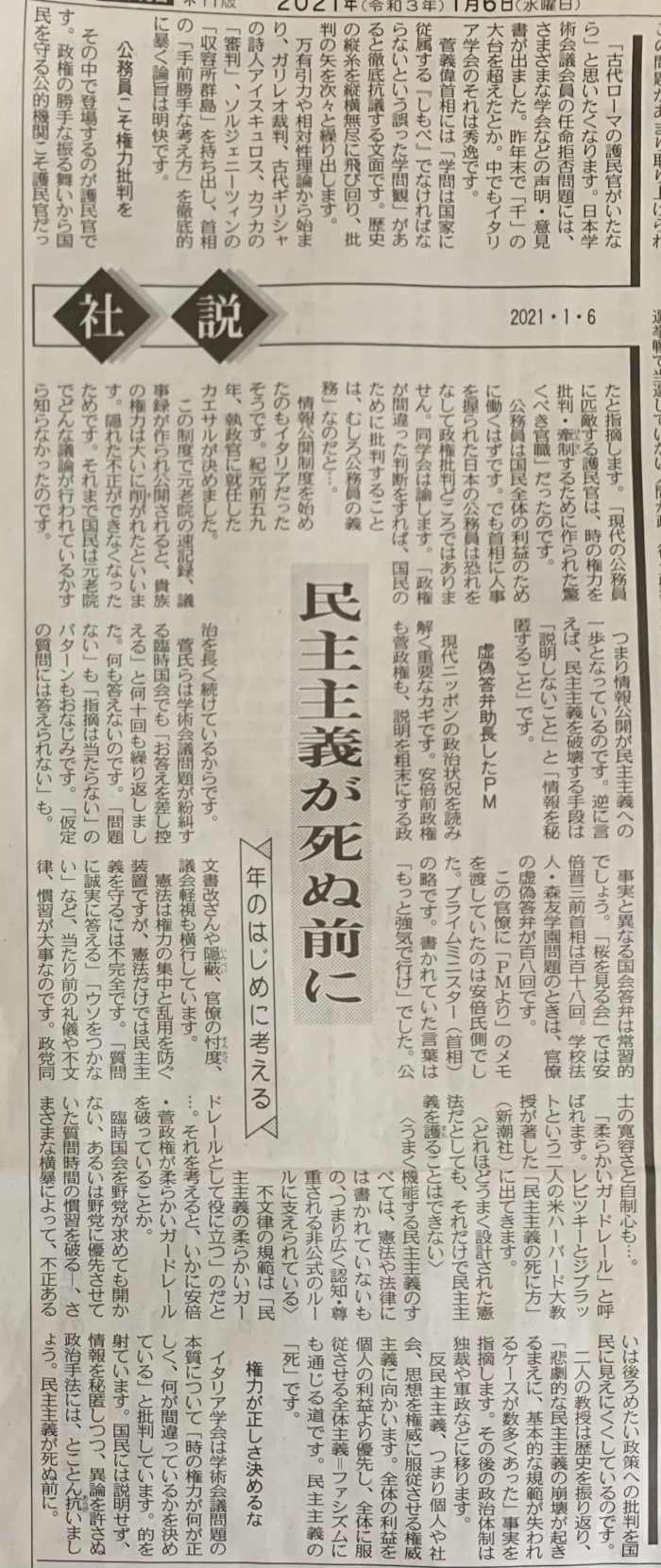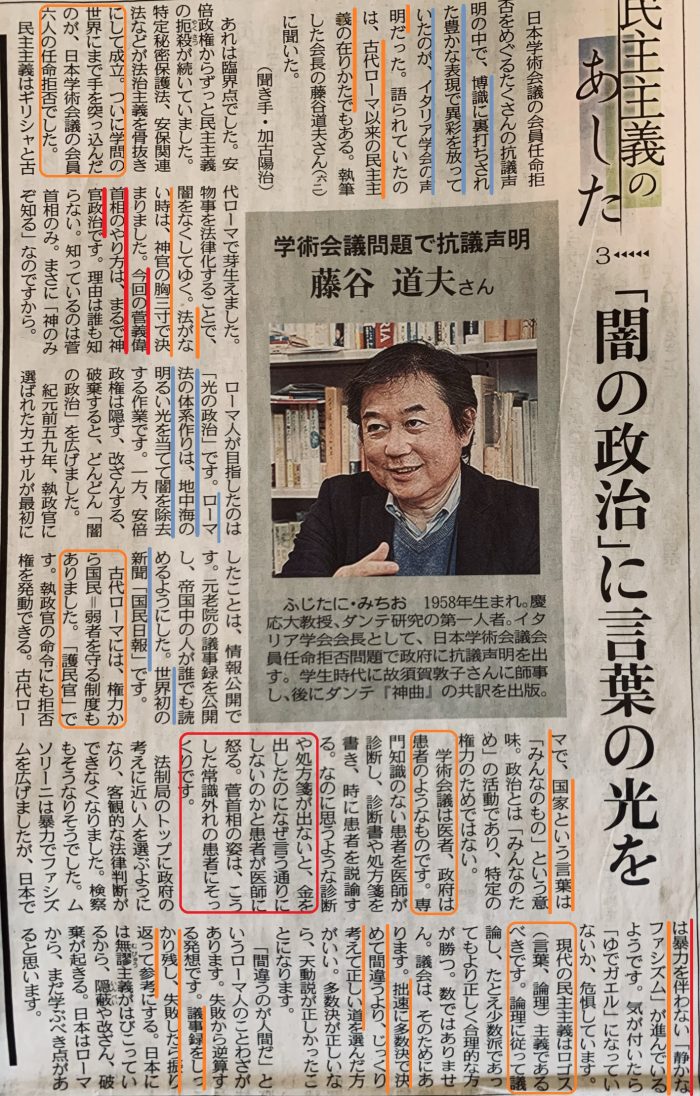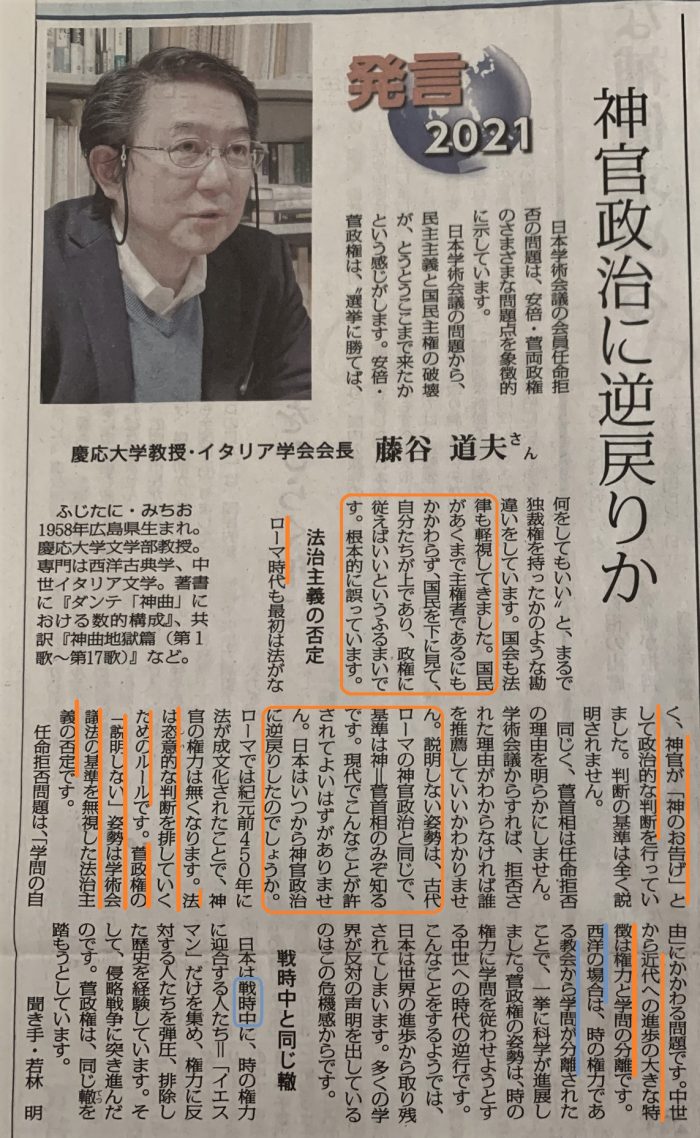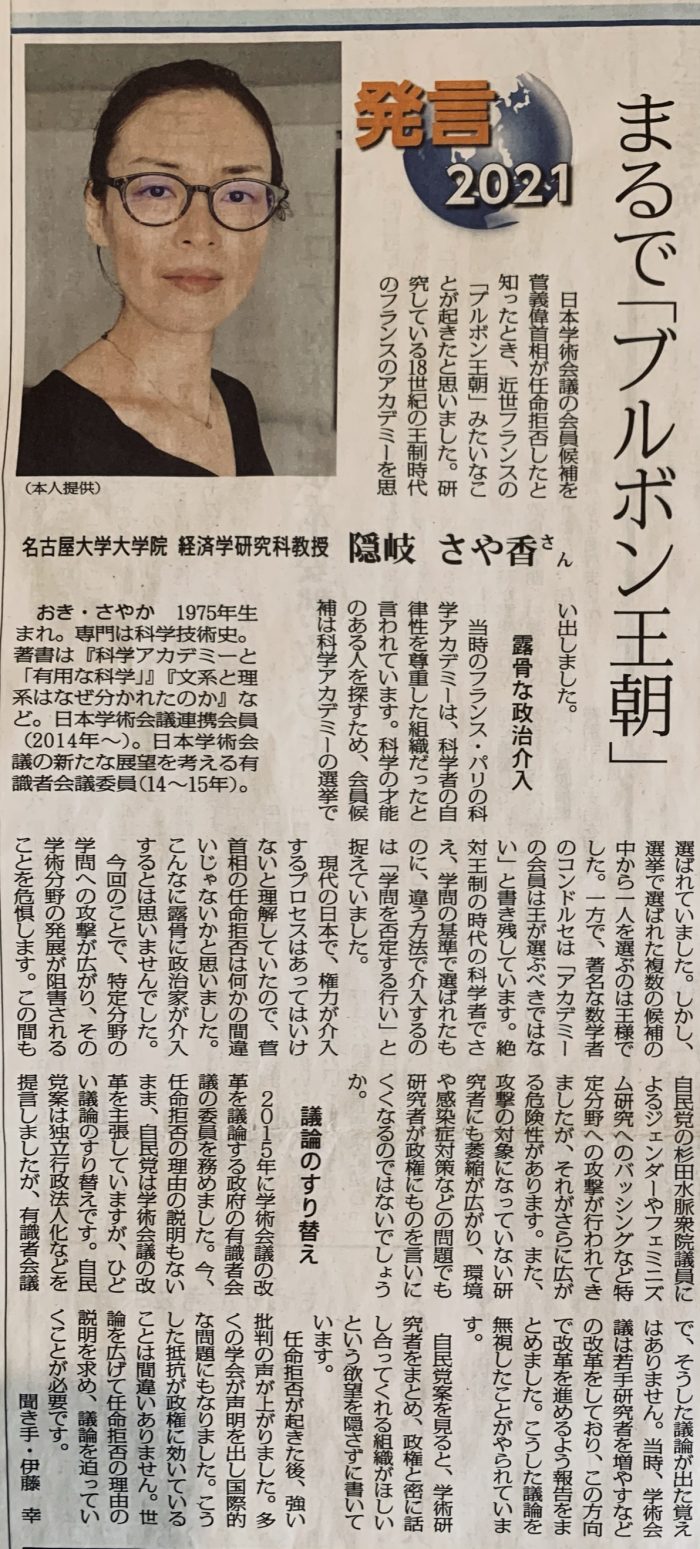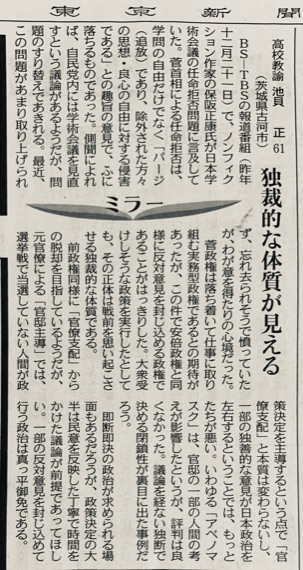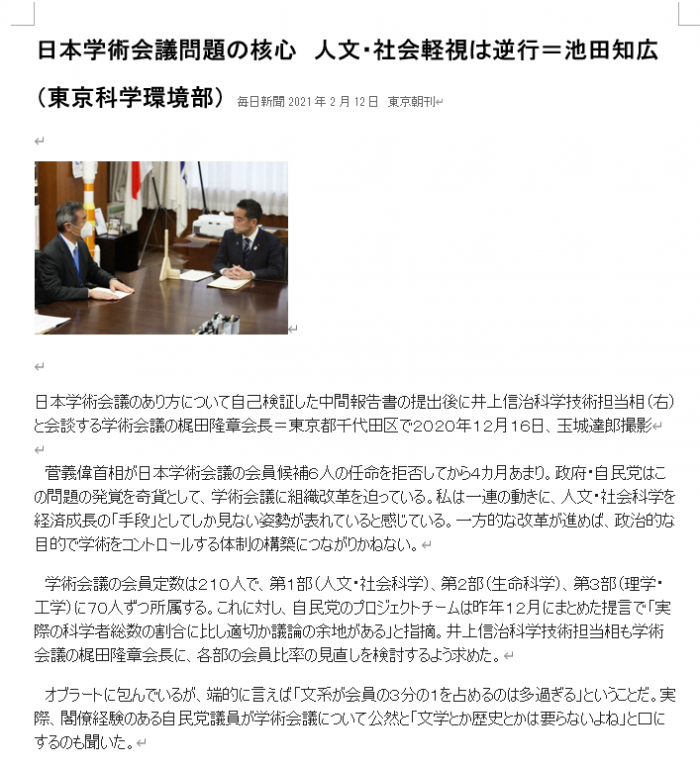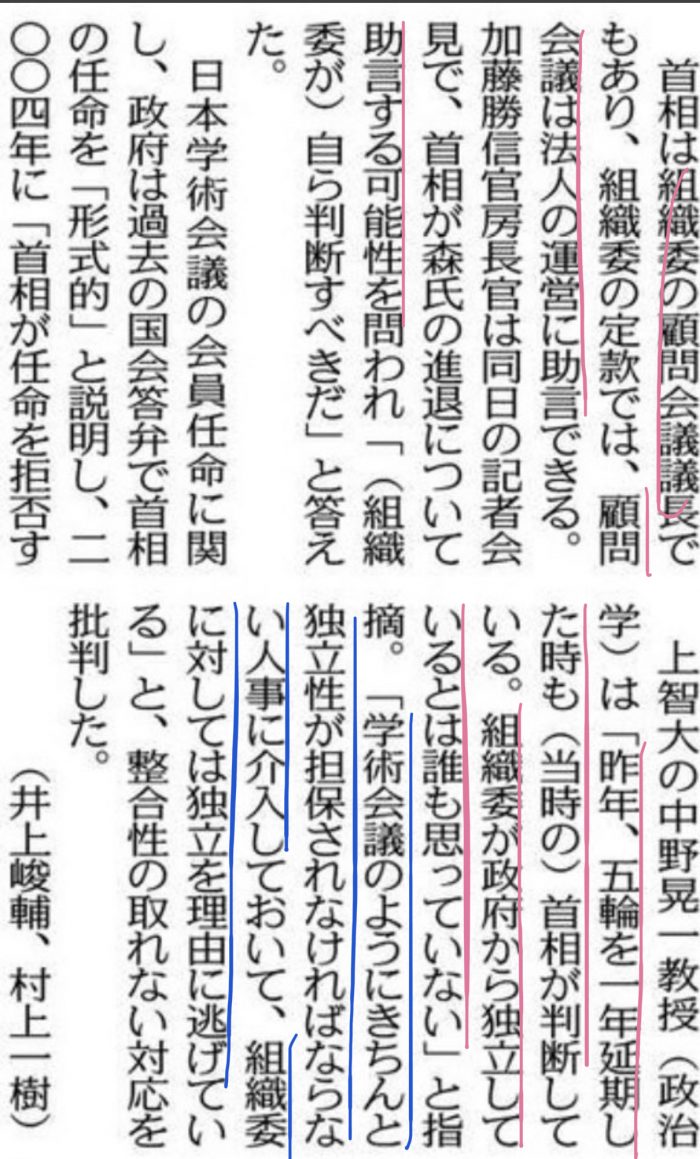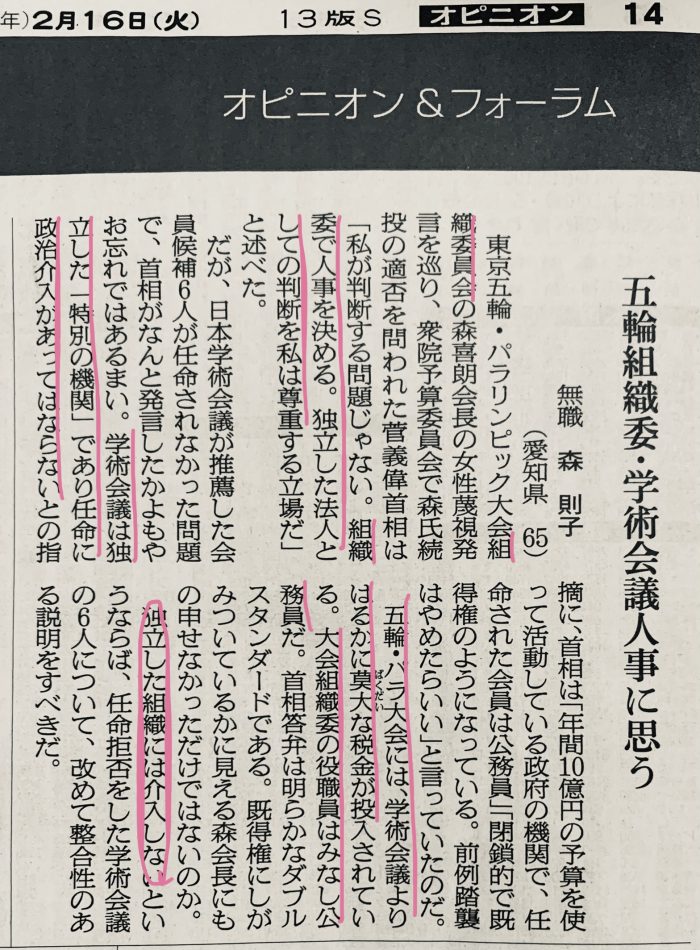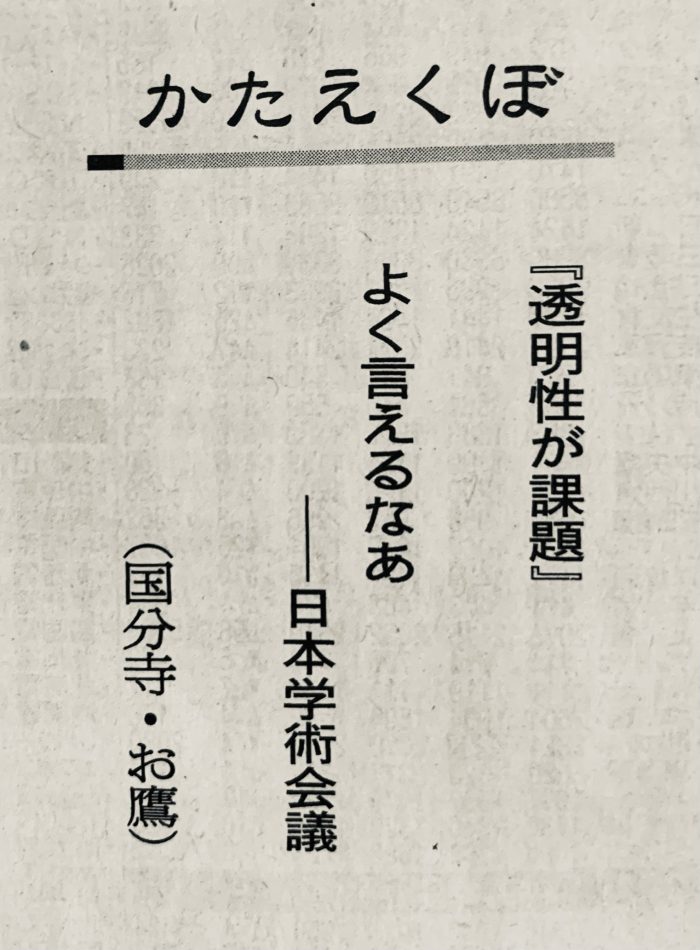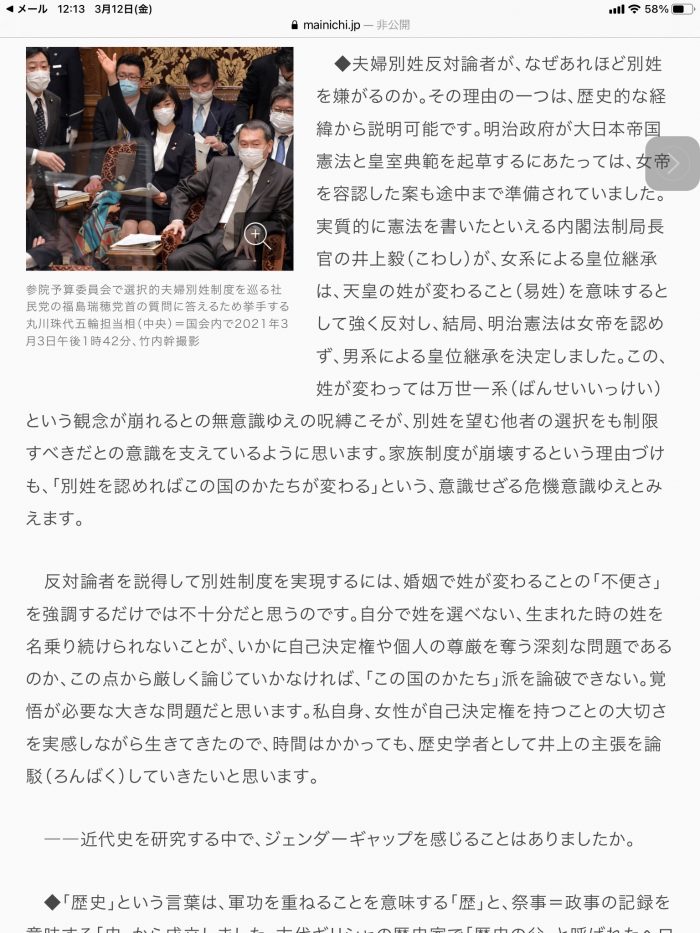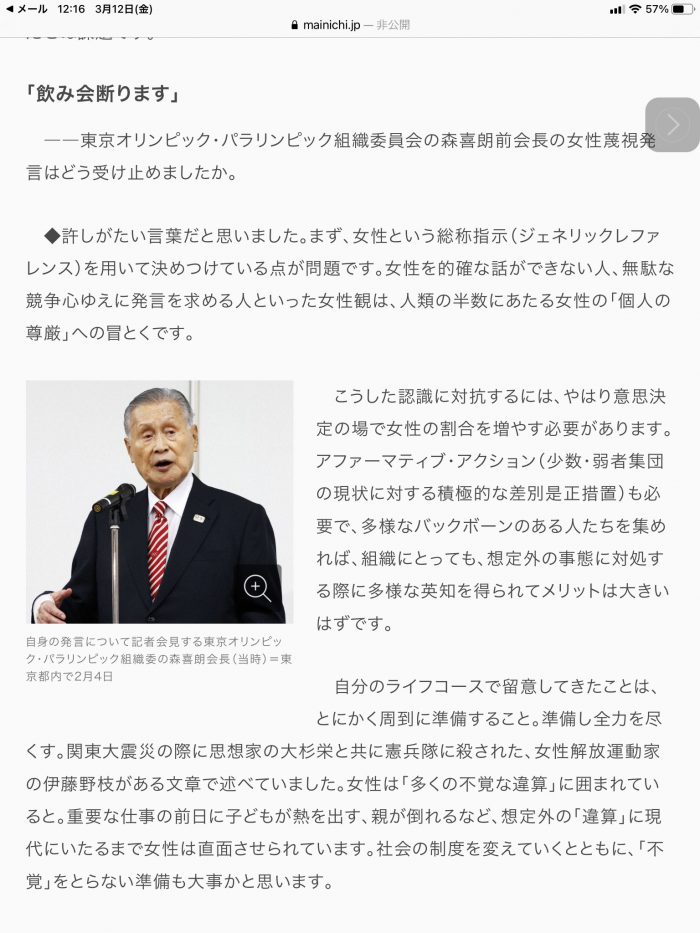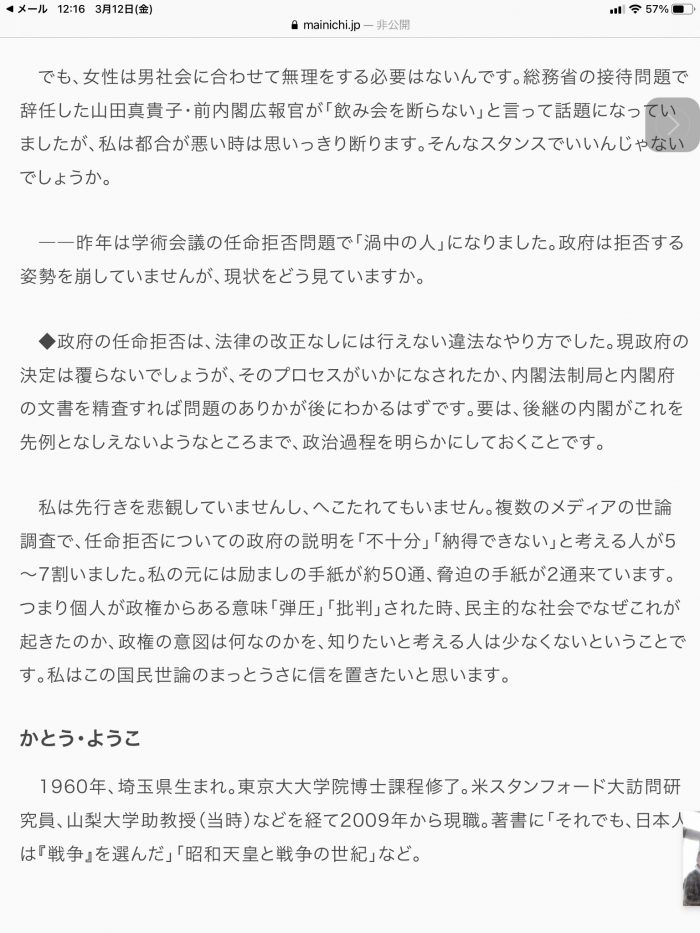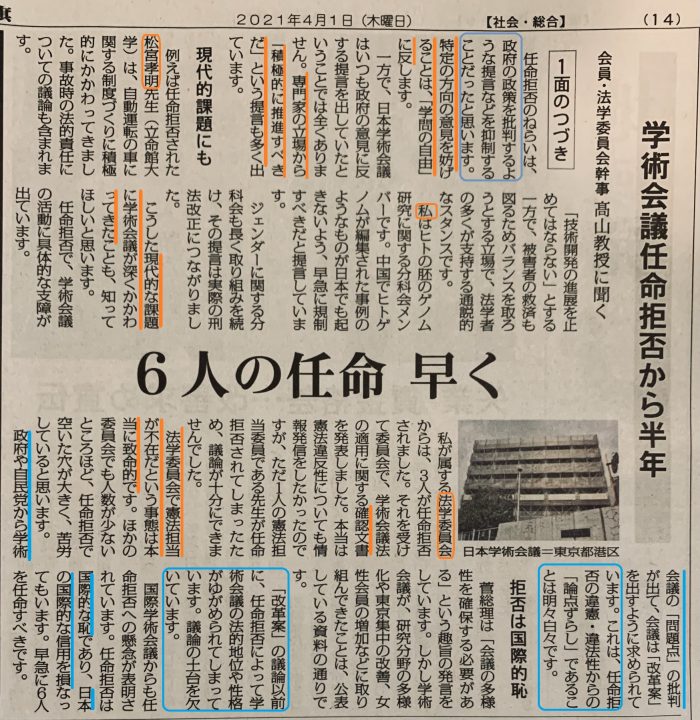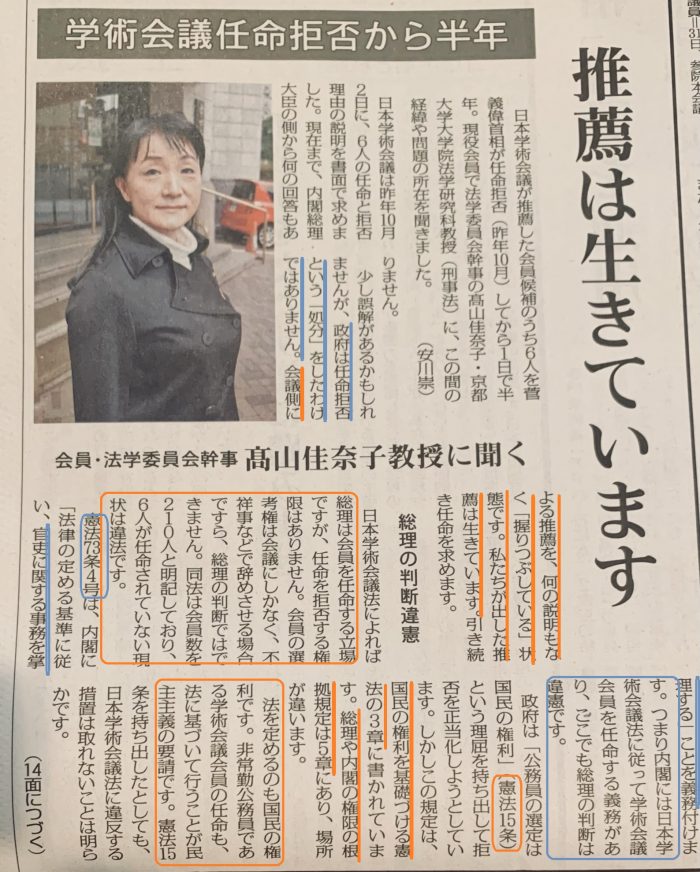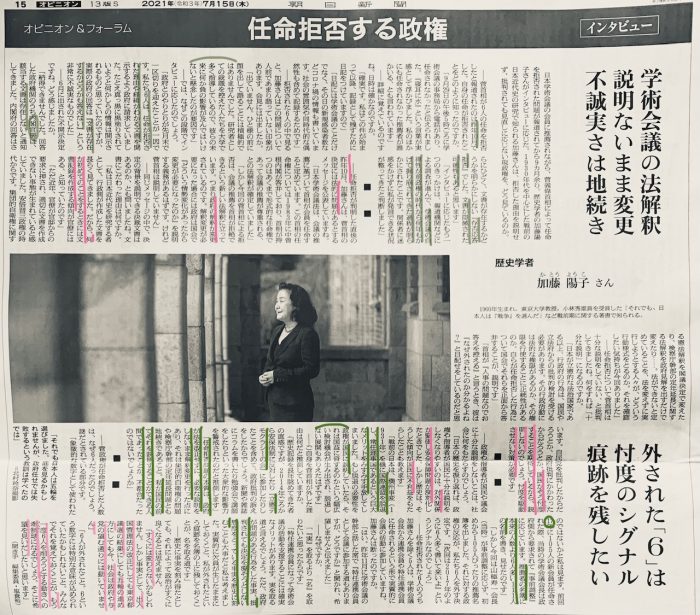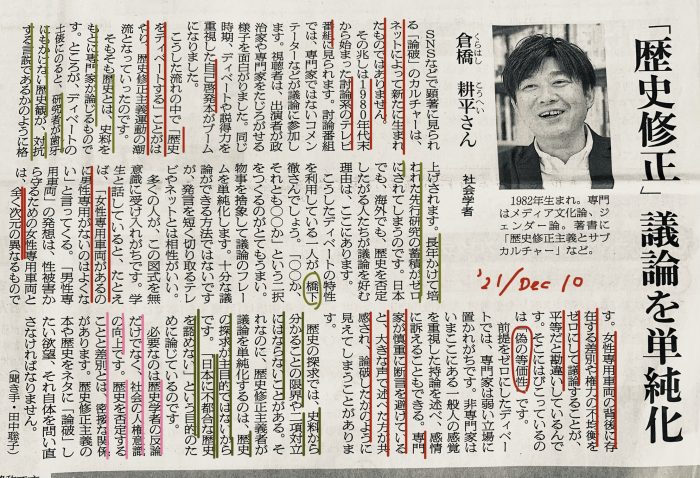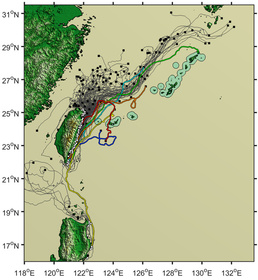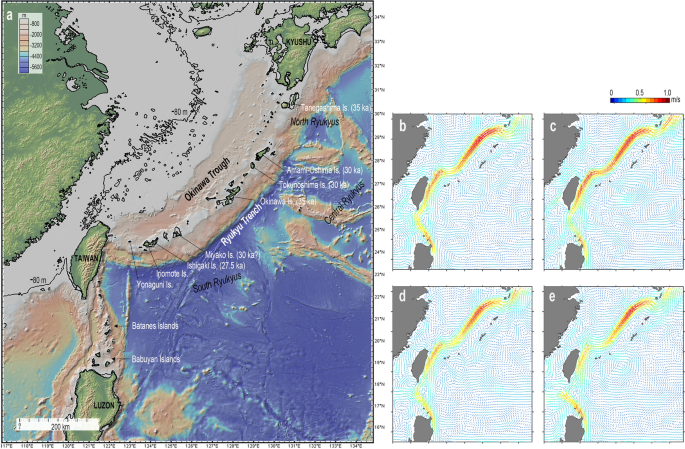Haiku, poem, 2021 Jan-Feb.
さきほどの冬菫まで戻らむか (対中いずみ)
冬の日溜まりでみつけた冬菫。なにげなく通り過ぎたあとその存在が心に響き、いつしか無視できないほどになっていました。小さな生命へそっと心を寄り添わせ、澄んだ静けさを感じさせる一句です。(季語=冬菫)
☆ 初詣帰り道なる冬菫
1/4に見たのは冬スミレなのかな?春がもう来ているのかとおもったけど・・・。(2021/1/10)
冬に咲くスミレの品種があるわけではなく、晩秋~初冬、または晩冬などの日当たりの良いあたたかい場所にたまたま咲いたスミレの呼び名である。寒の間に見つけたものは寒菫(カンスミレ)とも言う。 ★ふるきよきころの色して冬すみれ (飯田龍太)
☆ 孫と巡る円覚寺庭カンアヤメ(円覚寺にて)
お寺巡りが趣味(ほかにも恐竜、日本の歴史、日本文学にも詳しい)の孫と北鎌倉の名園を歩きました。(2021/1/10)
いつぽんの冬木に待たれゐると思へ (長谷川櫂)
「思へ」という命令形に切迫感があり、切実な思いが心を捉える一句です。いろいろ想像をかきたてますが、自分を待つ、孤高な佇まいの一本の冬木は、自らがめざす厳しい世界の象徴でしょうか。(季語=冬木)
狸汁吾子還暦となりしかな (栗林千津)
なんと我が子が還暦を迎えました。私も年をとるはずです。背中を丸め、狸汁を啜ります。(季語=狸汁)1/30
☆ やわらかなハスキーヴォイスに思う過ぎし日
玉置浩二の新しいアルバムChocolate Cosmosを聴きながら思う懐かしい日々。でも遠い日ではない、すべて今の私につながっているから。1/30
花言葉:「過ぎにし恋」「恋の終わり」「移り変わらぬ気持ち」
☆ “白い花(Snow Flower)”誰と見るのか Kim Taehyung
あの歌姫Sumi Joもハマった(言葉が蓮っ葉だけどこれが一番近い) BTS “V” Kim Tae Hyoung”(김태형,金泰亨 ) の美しい Love Song “Snow Flower.” 雪を表す白い花(하얀 꽃들)はある種の幸せの象徴だという。1/30
☆ 春浅し空に映えるや梅の花 (安立寺にて)
☆ 立春の庭に小さき黄水仙 (龍華寺にて)
早春の寺。歳時記で季語を調べて2句。梅の花と空の青さに・・・。 2/3
甘草の芽のとびとびのひとならび(高野素十)
種を蒔いたとおりに並んでとびとびに芽を出した甘草。小さな芽の勢いを感じさせます。昭和4年作。客観写生の名句として虚子が高く評価し、秋桜子が些末な「草の芽俳句」と酷評、対立のきっかけとなった句です。(季語=甘草の芽)
✩ 掲示板の番号指しつ孫に春
孫娘にうれしいたくさんの中学入学合格通知。3年間の努力が報われる幸せを希望に変えて、これからも良い性格のままで成長していってほしい! 2/14

手榴弾一個ばかりの命にて 語れぬ日々を兵士は生きたり 息ひとつ吸いてこの世に生まれ来る ものみな息を吐きて逝くなり この人をいつ手放そか曼殊沙華 風に揺れても屹立している(池田理代子)
✩ “17歳年上の人”とTaehyung言う その胸のうち知るすべもなし 2/14
三渓園にて; ✩ 紅梅のかそけき香りや春の宵 ✩ 梅の香よ思い出さすなはるか遠き日 ✩ その香り我が幼子かかの人か ✩ 池の端にネコヤナギ見ゆ懐かしき ✩ 山茱萸の黄の色ゆかし三渓内苑 2/24
Pleasant flames, Pedals and blooms. Spring time is here (Pyrrha)
✩ 梅香る春の日いろりの匂いかな (A) on the GTT 2014. March
夢の世やぺんぺん草の遊びせむ(甲斐由起子)
ぺんぺん草は、春の七草のひとつ、薺(なずな)のことです。道端や野でよく見かけます。夢のように過ぎるこの世で、ぺんぺん草をくるくると回して小さな三角の実を触れ合わせ、そのかすかな音を楽しみましょう。(季語=ぺんぺん草)