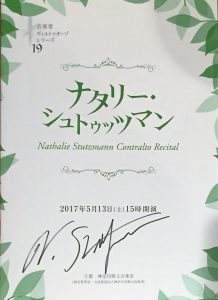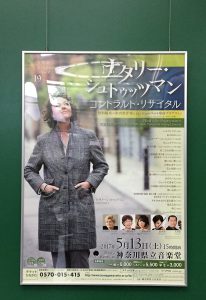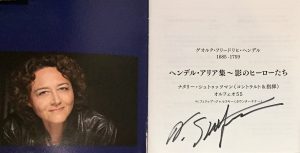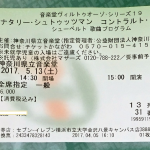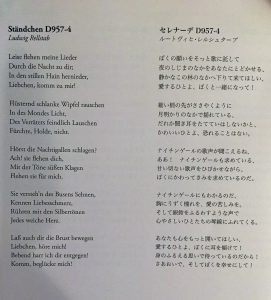♪ Lascia ch’io pianga
Lascia ch’io pianga de Rinaldo de Händel
Sissel Kyrkjebo

Italian LyricsLascia ch’io pianga Il duolo infranga |
English TranslationLet me weep The duel infringes |
|
|
私を泣かせてください どうか泣くのをお許しください この過酷な運命に どうか自由にあこがれることをお許しください わが悲しみは、打ち続く受難に鎖されたまま 憐れみさえも受けられないのであれば |